楽天証券トウシル「なんとなくから卒業!実践・資産形成術」にコラムを提供しています(2025/2/25掲載)。 https://media.rakuten-sec.net/articles/-/47977


楽天証券トウシル「なんとなくから卒業!実践・資産形成術」にコラムを提供しています(2025/2/25掲載)。 https://media.rakuten-sec.net/articles/-/47977


YouTube チャンネルに新作動画をアップしました! 春闘では賃上げ交渉の行われるシーズンです。今年もおそらく、賃上げの実現する企業が多いことでしょう。それが物価上昇率をしっかり上回れば理想的です。
ところで、賃上げが何年も連続し、物価上昇基調が確定してきたとき、もうひとつ交渉しなければいけないテーマがあります。それは「退職金・企業年金制度」の水準引き上げです。
労働組合で数十年行われてこなかったテーマだけに、交渉ノウハウが失われている可能性があります。まずは議論のスタートまで今年の春闘でこぎ着けたいところ。
Yahoo!ニュースエキスパート掲載記事はこちらです →労組必見!賃上げ交渉の次に必要な「退職金引き上げ」交渉とは?(実質10%ダウン?会社も忘れてるかも) https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/9615fe24ec1a3925c81a14e8af0dd472a6c3d52c

YouTube チャンネルに新作動画をアップしました! https://www.youtube.com/watch?v=AQLVcyzHgXI
近年国民の投資枠として普及しているNISAですが、「国内株を買うべきだ」「海外への投資は国富の流出である」という議論が時折出てきます。「国内投資枠」の制限議論まであるとしては穏やかではありません。 NISAは国内の株価対策のために投資をしなければいけないのか、海外への投資をすることは本当に国富の流出で日本に不利益を与えるものなのか、整理をしてみたいと思います。
Yahoo!ニュースエキスパートに掲載記事はこちら → 労組必見!賃上げ交渉の次に必要な「退職金引き上げ」交渉とは?(実質10%ダウン?会社も忘れてるかも) https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/9615fe24ec1a3925c81a14e8af0dd472a6c3d52c
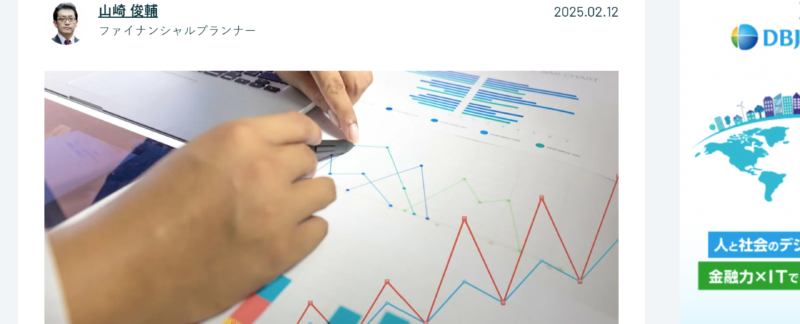
finaseeに「【資産運用】インデックスvsアクティブ議論に正解はない! 向き・不向きを考える時に判断軸となるのは…」を掲載しています(2025年2月12日)。
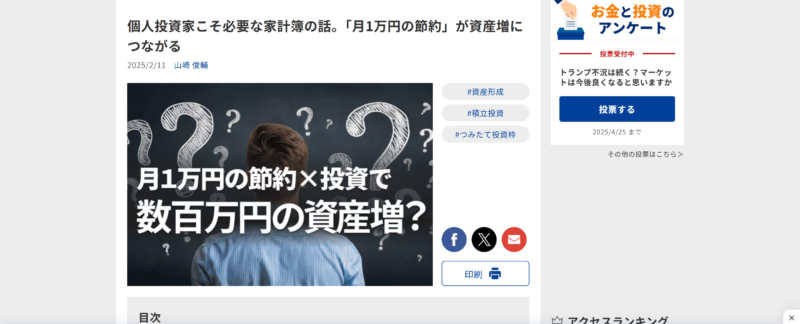
楽天証券トウシル「なんとなくから卒業!実践・資産形成術」にコラムを提供しています(2025/2/11掲載)。

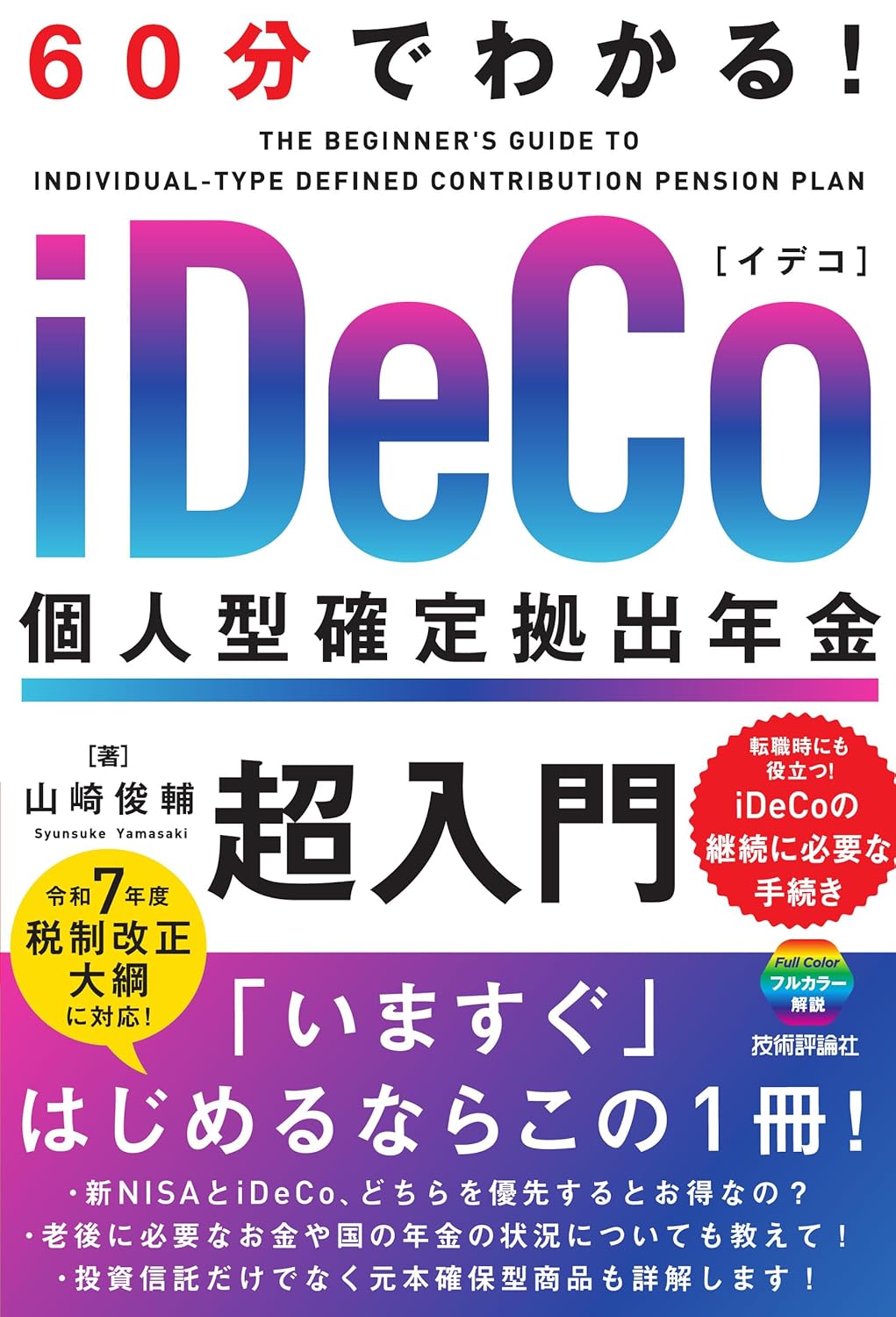
mymoにコラムが掲載されました。ストレス時代の幸せの見つけ方、秘訣はいろんな○○を見つけるコト https://mymo-ibank.com/money/8585